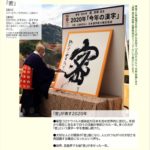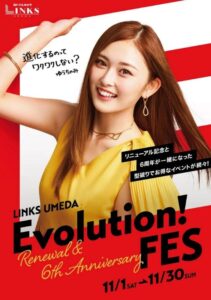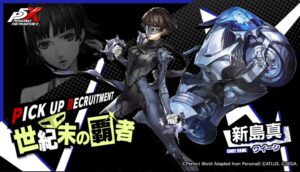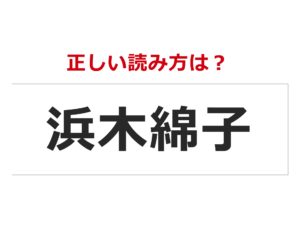来年3月に開催を控える第6回WBCで、日本国内の全47試合はNetflixが独占でライブ配信する見通しとなり、地上波の生中継は消える方向となった。前回2023年大会は決勝・日本―米国が平日午前にもかかわらず関東世帯視聴率42.4%。日本戦7試合はすべて40%超えで、国民的同時視聴を生み出した。今回は視聴形態が大きく変わる。
日本国内のライブ視聴はNetflixに一本化。日本向けの権利は主催側が直接Netflixに付与したとされ、従来の「国内とりまとめ→各局へ再配分」という経路は採られていない。
“地上波ゼロ”に向かった背景
最大要因は権利料の高騰だ。2023年の大成功が国際的な相場感を押し上げ、広告ベースの地上波では採算が合いにくい状況になった。加えて今回は主催者が直売の独占契約を構成。結果として地上波の同時放送は契約上、実現が難しくなった。
同時体験を加速させてきたのは、無料で一斉に届く地上波という“到達力”だった。配信独占では加入とネット環境の準備が前提となり、学校や職場、商店街で自然発生的に盛り上がる構図は作りにくい。大型のパブリックビューイングも、配信サービスの規約上は別途の許諾が必要になるケースが多い。
それでも「どうしようもない事情」
主催直売の独占契約、権利料の高騰、そして“無料放送で守る”類の制度的担保が国内に乏しいこと。この三つが重なり、地上波と配信の並走モデルは崩れた。テレビ関係者は「同時放送は難しかった」と話す。ニュースや情報番組でのダイジェスト利用は可能とみられるが、ライブの同時到達という価値は代替しにくい。
ライブで追うならNetflixへの加入が必要になる。家庭内の同時接続や回線帯域を含む視聴環境の準備は早めに進めたい。店舗や学校行事で上映を検討する場合は、許諾の要否を個別に確認するのが無難だろう。
「地上波+配信」の二段構えで作ってきた熱量は維持しにくい。一方で、配信独占が視聴体験の新しい標準になる可能性もある。鍵を握るのは、ピーク時の同時接続に耐える配信品質と運用だ。勝ち進むほど、プラットフォームの力量が問われる大会になる。