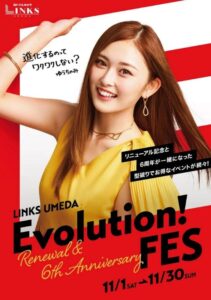日本のスポーツ史の頂点に立つ男・長嶋茂雄の物語は、1936年(昭和11年)、千葉県印旛郡臼井町(現・佐倉市)で産声を上げた。
目次
故郷・佐倉で燃やした野球への原点
「ミスター」の少年時代は、意外なことに熱烈な阪神タイガースファンだったという事実は、今も語り継がれる逸話だ。土手で泥まみれになって白球を追いかけ、青竹を削ったバットと、母親が裁縫したグラブが彼の最初の相棒だった。
高校は地元の佐倉一高に進学。この頃から長嶋の非凡な才能は頭角を現す。特に、南関東大会で放ったという推定107メートルにも及ぶ特大ホームランは、規格外のパワーを持つ男の出現を予感させた。
高校卒業後、長嶋は東京六大学野球の名門・立教大学へ進む。ここでは後に南海ホークスのエースとなる杉浦忠、チームメイトの本屋敷錦吾と共に「立教三羽烏」として猛威を振るう。当時、国民的熱狂の中心だった六大学野球で、長嶋は通算8本塁打という新記録を樹立。その華麗な守備と豪快な打撃は、すでに全国のファンを魅了し、彼の周囲には常に人だかりができていた。
意外だった巨人入団と「背番号3」の重み
大学卒業を前に、長嶋を巡る争奪戦は熾烈を極めた。特に有力視されていたのは、当時名将・鶴岡一人監督が率いる南海ホークス(現ソフトバンク)だった。しかし、最終的に長嶋の母親の「東京で野球をやらせたい」という願いと、読売ジャイアンツの正力松太郎オーナーの執念の勧誘により、当時の最高額とされる契約金で巨人入りを決断。
1958年、背番号「3」を背負ってプロの門を叩いた「ミスター」は、ただのスター候補ではなく、「時代を変える男」として、その運命の歯車を大きく回し始めたのだ。
国民を熱狂させた「天覧試合」のサヨナラ弾
長嶋茂雄という存在を「ひとりのスター選手」から「国民的スーパースター」へ押し上げた決定的な瞬間に触れないわけにはいかない。
1959年6月25日。後楽園球場で行われた対阪神タイガース戦。この試合は、昭和天皇・皇后両陛下がご観戦された、史上空前の「天覧試合」だった。
試合は息詰まる展開。4対4の同点で迎えた9回裏、一死満塁。打席には長嶋茂雄。マウンドには、後に長嶋の良きライバルとなる阪神のエース、村山実。
重い緊張感と、球場を包む異様な静寂の中、長嶋は真ん中高めに投じられた渾身のシュートを、全身全霊を込めてフルスイングした。打球は左翼スタンドへ一直線。劇的なサヨナラホームランとなり、長嶋はガッツポーズをしながらダイヤモンドを駆け抜けた。
この一打が、単なる一試合の勝利以上の意味を持った。この日を境に、プロ野球人気は大学野球人気を完全に凌駕し、「長嶋茂雄」という名前は、野球を知らない者でも知る日本のヒーローの代名詞となった。「スーパースター」とは、この瞬間に生まれた言葉と言っても過言ではない。23歳の若者が放った、勝利への執念と華麗なドラマツルギーは、日本中に熱狂の渦を巻き起こしたのだ。
ON砲の誕生と絶対王者の化学反応
長嶋がプロ入りした1958年。彼は瞬く間に日本の野球界の「顔」となったが、真の「不滅の時代」は、翌年、一人の若き強打者との出会いによって始まった。その男こそ、一本足打法で世界の本塁打王となる王貞治である。
1959年、巨人に加入した当初の王は伸び悩み、低打率に苦しんでいた。しかし、荒川博コーチの指導のもと、一本足打法を確立し、天才的な才能を開花させる。
ここに、天性の明るさと勝負強さでファンを魅了する動の「長嶋」と、徹底した努力と哲学的ともいえるストイックさを持つ静の「王」という、あまりにも対照的な二人の強打者が揃った。この二人が打線の中核を担い、「ON砲」として機能したとき、読売ジャイアンツは球史に類を見ない絶対的な強さを誇るチームへと変貌したのだ。
川上哲治監督のもと、二人は1965年から1973年まで、空前絶後のリーグ9連覇、通称「V9」を達成。このV9時代こそが、日本のプロ野球が最も熱狂し、最も国民の関心を集めた黄金時代に他ならない。
長嶋は主に3番を打ち、王貞治が4番を務めることが多かったが、時には打順を入れ替えて相手投手を撹乱。その破壊力はまさに異次元だった。
長嶋茂雄の個人タイトル:首位打者6回、打点王5回、本塁打王2回、MVP5回。
通算成績:2471安打、444本塁打、1522打点。
彼の成績は、王貞治が持つ本塁打記録のような「世界一」の派手さこそないかもしれないが、勝負どころでの一打、チームの勝利に直結する一打の多さでは、誰も彼に並ぶことはできない。まさに「記録よりも記憶」という言葉は、長嶋のためにあるのだ。
規格外の強さを生んだ「ミスターの華」
長嶋茂雄の凄さは、単なる成績では説明がつかない。彼には、観客の期待を裏切らない「何か」があった。
長嶋は、野球を「ショー」として捉えていた唯一の存在だった。誰よりも華麗な守備、誰よりも大きなガッツポーズ、そして誰よりも劇的なホームラン。
最も象徴的なエピソードは、彼のデビュー戦(1958年4月5日)の屈辱からの復活劇だ。国鉄のエース・金田正一から4打席連続三振に倒れ、プロの洗礼を受けた。しかし、長嶋は金田との通算対戦成績で、最終的に打率.313、18本塁打と圧倒。屈辱を倍返しにして、最大のライバルを打ち砕いたのだ。
また、1968年の阪神戦、相手投手のバッキーとの間で大乱闘が起きた直後、長嶋はマウンドに上がったばかりの権藤正利から、怒りを込めた特大ホームランを放っている。全身から迸る「闘志」をそのまま打球に乗せてしまう、規格外の精神力と勝負強さ。これこそが、「ミスター」がファンを熱狂させた所以である。
幻のメジャー挑戦
長嶋への熱視線は、国内だけにとどまらなかった。
1966年頃、当時ロサンゼルス・ドジャースのオーナーであったウォルター・オマリー氏が、「長嶋をドジャースに譲って欲しい」と巨人側に打診していたという、今では知る人ぞ少ないエピソードがある。オマリー氏は、長嶋の規格外の才能と、観客を惹きつけるスター性を評価していたのだ。
しかし、当時の巨人オーナー・正力松太郎氏は、「長嶋が抜ければ日本の野球は10年遅れる」と断固として拒否。この判断により、長嶋はメジャーの地を踏むことはなかったが、それは同時に、彼が「日本の至宝」として、日本のプロ野球人気を牽引し続けるという運命づけられた道であった。
V9という偉業を成し遂げる中で、長嶋は球界の頂点に立ち続けた。しかし、絶対的な強者にも、いつか終わりは訪れる。その終わりが、長嶋にとっての新たな「伝説」の始まりとなることを、この時のファンはまだ知る由もなかった。
絶対的な強さを誇った「ON砲」の黄金時代にも、終わりは静かに訪れた。
力の衰えと引退への葛藤
1970年代に入り、長嶋茂雄は30代後半を迎える。全盛期のような打球の勢いは徐々に失われ、快音が野手の正面を突くことが増え始めた。天性の才能と勝負勘を持つ「ミスター」自身が、自らの力の衰えを最も痛感していたに違いない。
その葛藤を象徴する出来事が、1973年、ヤクルトとの一戦で起こった。
8回の攻撃、巨人はチャンスを迎えるが、ヤクルトのバッテリーは王貞治をなんと5打席連続で敬遠し、長嶋との勝負を選んだのだ。この時、長嶋は内野ゴロに倒れてチャンスを潰してしまう。
相手チームから「王と勝負するより、長嶋との方がまだマシだ」と判断されたこの屈辱的な事実は、長嶋の胸に深く突き刺さった。球界の中心は、静かに王貞治へと移り変わっていたことを、長嶋は受け止めざるを得なかったのだ。
涙の引退表明と「V10」消滅
そして、運命の1974年が訪れる。
V9を達成した巨人軍は、この年、10連覇(V10)を目指して戦ったが、中日ドラゴンズの前に苦戦を強いられた。10月12日、巨人のV10が消滅すると同時に、長嶋はかねてより胸に秘めていた引退の決意を固める。
10月14日、後楽園球場での対中日ダブルヘッダー。これが長嶋茂雄の現役最後の舞台となった。
第1試合では、最終打席でセンターへホームランを放ち、現役最後のホームランを記録。第2試合では、現役最後の打席でレフト前ヒットを放ち、最後まで「ミスター」らしい勝負強さを見せつけた。しかし、彼の心は、もう次のステージへと向かっていた。
「我が巨人軍は永久に不滅です!」
試合が終わり、グラウンドに立つ長嶋は、球団関係者の制止を振り切って、自らの意志でファンへの感謝を示すため、場内一周を始めた。
外野席にまで足を運び、詰めかけたファンの大声援と「長嶋」コールに応える「ミスター」。その目には大粒の涙が溢れ、嗚咽を漏らしながらファンに手を振り続けた。華やかな長嶋の、心からの、そして最も人間的な瞬間だった。
そして、その後の引退セレモニーで、彼は日本のスポーツ史に永遠に残る、あの言葉を宣言する。
「私は、今日、引退をいたしますが、我が巨人軍は永久に不滅です!」
この言葉は、単なる現役引退の挨拶ではない。
V10を逃し、川上監督が勇退した「古き良き巨人軍」が終焉を迎える中で、長嶋は、巨人軍の「魂」、そして「プロ野球が日本人に与える夢」そのものが、これからも永遠に続くのだという希望のメッセージを国民に発したのだ。
スーパースター・長嶋茂雄の現役時代は終わった。だが、その華と魂は、そのまま「監督」という新たな肩書となって、日本の野球界に再び旋風を巻き起こすことになる。
「我が巨人軍は永久に不滅です」の宣言からわずか半年、長嶋茂雄はユニフォームを脱いだばかりのその身で、巨人軍の第15代監督に就任する。背番号は、現役時代とは違う「90」。それは、スーパースターとしての「長嶋茂雄」とは別の、「指導者・長嶋茂雄」としての新たな戦いの始まりだった。
第1次監督時代の「理想と現実のギャップ」
長嶋監督が目指したのは、前任の川上哲治監督が築いた「管理野球」とは対極にある、自由で伸び伸びとした「クリーン・ベースボール」だった。選手一人ひとりの自主性を重んじ、「ミスター」自身の華やかさをチームに注入しようと試みた。しかし、理想は現実の前に脆くも崩れ去る。監督1年目の1975年、巨人軍は球団史上初となる最下位という屈辱を味わう。
長嶋の采配は、ファンにとっては予測不能な「ミスターマジック」だったが、現場にとってはしばしば理解不能な「ミスター采配」として映った。ある選手の証言によれば、「サインが相手にバレバレだった」「小言が現実になるジンクス」など、データや理詰めではない感性の野球は、結果を伴わないとただの迷走と見なされた。
それでも長嶋は諦めなかった。翌1976年には、トレードで張本勲、加藤初といったベテラン・実力者を獲得し、チームを立て直す。そして、見事、最下位からの奇跡のリーグ優勝を成し遂げる。これが「ミスター」の真骨頂。一度どん底に落ちても、持ち前の熱と運で一気に頂点へ駆け上がる、その劇的な展開こそ、長嶋劇場だった。
監督時代、長嶋を語る上で避けて通れないのが、1978年から翌年にかけて球界を揺るがした「江川事件(空白の一日)」だ。
長嶋監督がこの騒動にどこまで関与していたかは不明だが、結果的に江川卓が巨人に入団し、当時のエース・小林繁が阪神へトレードされるという、球史に残る大事件となった。この余波は大きく、1979年には阪神の小林に8連敗を喫するなど、チームは低迷。1980年限りで、長嶋は第1次政権の辞任という無念の結末を迎えることになる。
長嶋チルドレンと国民的熱狂
12年のブランクを経て、1993年、長嶋茂雄は再び巨人軍の監督として舞い戻る。この時、背番号は再び背番号3に戻り、ファンは熱狂的な歓迎をもって「ミスター」を迎えた。
第2次政権の最大の功績は、若手育成にあった。
彼は、後にゴジラとしてメジャーへ羽ばたく松井秀喜に対し、監督自ら連日、特訓を施した。また、天才的な打撃センスを持つ高橋由伸を育て上げ、多くの若手選手を指導。彼らは「長嶋チルドレン」と呼ばれ、ミスターの哲学と熱血指導のもと、大きく成長していった。長嶋は、選手の才能を見抜き、それを引き出す天賦の才を持っていたのだ。
伝説の「10.8決戦」とON対決
長嶋監督の第2次政権下で最も熱狂的な瞬間の一つが1994年のシーズン最終戦、中日ドラゴンズとの「10.8決戦」だ。
同率で迎えた最終戦は、プロ野球史にも前例のない緊張感。この死闘を制して長嶋は監督として初のリーグ優勝を果たす。この時の感動と興奮は、当時のプロ野球人気を爆発的に押し上げた。
そして、2000年。長嶋監督率いる巨人軍は、宿命のライバル、王貞治監督率いるダイエーホークスと日本シリーズで激突する。「ON対決」として日本中が注目したこのシリーズを制し、長嶋は監督として悲願の日本一を達成。現役時代から目標に掲げた監督としての頂点に立ち、まさに有終の美を飾った。
2001年限りで監督を退任した長嶋茂雄。波乱に満ちた監督人生は、時に迷走し、時に奇跡を起こしたが、その根底には常に、野球を愛し、ファンを愛する「ミスターの熱血」が燃え盛っていた。
2001年に第2次監督を勇退した長嶋茂雄は、読売巨人軍の「終身名誉監督」という、文字通り唯一無二の肩書に就任した。彼の存在は、もはや一球団の監督や、一時代の名選手という枠組みでは収まらない、日本のスポーツ界そのものの象徴となった。
師弟での国民的栄誉賞
長嶋茂雄の功績は、野球のグラウンドを飛び出し、日本国の文化と国民の精神にまで影響を与えたと認められる。
2013年、長年にわたってプロ野球の発展に多大なる貢献を果たし、国民に夢と感動を与え続けた功績が認められ、松井秀喜とともに国民栄誉賞を受賞。これ以上ない「師弟関係の結実」となった。
さらに2021年には、野球界の人物として史上初となる文化勲章を受章。これは、長嶋茂雄が「野球人」を超え、「文化人」「偉人」として、日本の歴史に名を刻んだ証である。その功績は国内にとどまらず、1988年にはローマ教皇からバチカン有功十字勲章を授与されるなど、早くから世界的な評価を得ていた。
闘病生活に見せた「燃える男」の執念
順風満帆に見えた「終身名誉監督」としての生活だったが、2004年に長嶋を病魔が襲う。脳梗塞を発症し、一時は危篤状態に陥った。
しかし、現役時代から常に「燃える男」であり続けた長嶋は、ここでも驚異的な執念を見せる。言葉のリハビリ、歩行訓練、そして自らバットを振る練習。その闘病と復活への努力は、病に苦しむ多くの国民に勇気を与えた。
2021年の東京オリンピック開会式では、病後にもかかわらず、公の場に姿を現し、聖火の最終ランナーの一人として参加。その姿は、病に打ち克ち、再び立ち上がった「ミスター」の、まさに人生をかけたガッツポーズであり、日本中に感動の嵐を巻き起こした。
永遠の光を放つ「長嶋茂雄という存在」
2025年6月3日、長嶋茂雄は89歳で逝去した。
しかし、長嶋茂雄という存在が残したものは、444本塁打という数字や、数々のタイトル、そしてV9という記録だけではない。彼がグラウンドで見せた華、夢、そして、勝負に懸ける無垢なまでの熱血こそが、日本人の心に永久に刻み込まれているのだ。
彼の死は、多くの日本人に大きな悲しみをもたらしたが、同時に、彼の言葉通り、「我が巨人軍」のみならず、「日本のプロ野球」は、長嶋茂雄が撒いた夢と希望という種によって、これからも永久に不滅であることを改めて確信させた。
日本が生んだ永遠に光り輝くスーパースター。その輝きは、時を超え、世代を超えて、これからも私たちを熱狂させ続けるだろう。