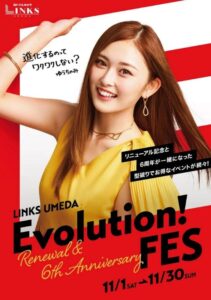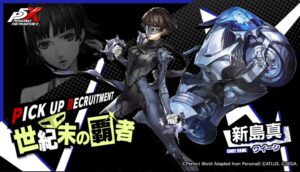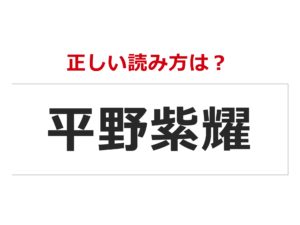“お笑い界の革命児”である松本人志の「言葉」は、常に笑いだけを目的に放たれたわけではない。そこには、笑いと同じ比重で「価値観」「線引き」「時代との摩擦」があった。だからこそ、彼の発言は賞賛と炎上の両方を呼び続ける。松本がなぜ叩かれ、なぜなお擁護され、なぜ「天才」と呼ばれ続けるのか。その理由は、過去の発言を脈絡なく並べるだけでは見えない。
松本人志の言動を辿ると、そこに一貫した“思想”が浮上する。「笑わせること」と「社会とズレること」は、松本にとって同義だったのではないか——ということだ。
「ワイドナショー」での発言
たとえば2014年、「ワイドナショー」で自殺に関する話題が取り上げられた際、松本はこう言った。「死んだらみんながかばってくれるっていう風潮がすごく嫌」
この発言についてネットでは議論が噴出。「生き方は勝ち負けじゃない」という批判と、「松本らしい」と肯定する声が真っ二つに割れた。
同番組で凶悪犯罪について言及した際も、こう述べている。「人間が生まれてくる中でどうしても不良品って何万個に1個、絶対これはしょうがない」
やはり炎上は避けられなかった。松本が語った「不良品」は、システムでも制度でもなく“人間”に向けられた言葉だったからだ。
これらは、単なる“失言リスト”ではない。むしろ松本の発言には、共通する“型”がある。「生きる/死ぬ」を「勝ち負け」で語り、「社会的な逸脱者」を「制度ではなく性質で語る」。松本人志は「社会が前提とする倫理の枠組み」を、最初から信じていないのだ。だからこそ、言葉が摩擦を生む。
そしてその摩擦こそが彼の“笑いの燃料”だったのではないか。
思想の源流はどこにあるのか
1994年に出版された『遺書』の中で、松本は「面白い奴の条件」を「ネクラ・貧乏・女好き」と定義した。これは、タレント本にありがちな“自己啓発”ではない。むしろ、世間が避ける要素を「面白さの源泉」と断言する「本音ありきの逆張り構造」だった。
また同書では、多くのレギュラー番組を抱えるテレビタレントについて「自分から『十四本やってます』などと、自慢げにアホ面して言うなばかたれ!」と綴っている。実名こそ出していないが、中山秀征のことを指しているのではと、当時のテレビ業界を騒然とさせた。
松本の価値観は“売れたかどうか”ではなく、“空気を変えたかどうか”に重きを置いている。だからこそ、後年のM-1、キングオブコント、IPPONグランプリなど「競技としての笑い」を生んだのも必然だった。
笑いを測る。笑いを競わせる。笑いを制度にする。これは、テレビの常識を書き換えるプロセスであり、同時に“松本人志という思想”が社会に可視化された瞬間でもある。
なぜ炎上し続けるのか
松本が叩かれる理由は、過去の発言内容そのものではない。「社会の変化に対し、松本の言葉がアップデートされていない」と見なされること、それが「炎上の正体」だろう。
しかし、それは一面的な見方である。裏を返せば「松本人志は自分の“思想の出発点”を裏切っていない」とも解釈できるのだから。松本にとって笑いとは、共感ではなく“ひっかかり”であり、時代にフィットすることより“ズレること”が価値だった。つまり、炎上こそが「松本人志の言葉が生きている証」でもある。
松本人志の“思想の根源”
ルールに寄り添うテレビタレントが増えた時代に、ルールそのものを揺らし続ける存在。言葉を間違えたのではなく、言葉の“置き方”を変えなかった人間。炎上と称される過去発言の数々は、破壊ではなく“姿勢の証拠”だ。松本人志とは、「時代との摩擦を笑いに変換する、最後の職人」なのかもしれない。
(松尾晶)